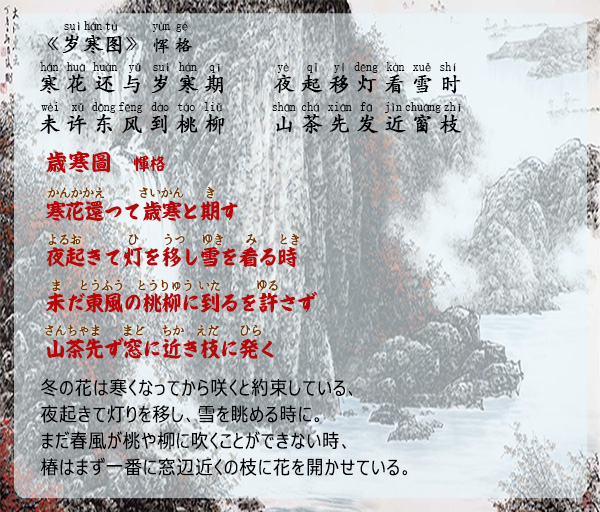作者、王維は盛唐の詩人。何度も紹介していますね。自然を詩に詠みこむことや山水画を得意としました。今日、紹介した詩は、そんな王維らしさがよく現れているのではないでしょうか。詩の中には「紅葉」の文字がありますが、目に浮かぶ情景は秋たけなわの艶々した紅葉ではなく、冷たい風に晒され枝に数枚残る紅葉です。荊渓は、地名です。湛然(たんねん)という天台宗の僧侶が住んでいた地です。王維も仏教に帰依していたといいますから、彼の詩にこの地名が登場するのも納得できます。夏の間はこんこんと流れていた水が秋、そして冬になると枯れて、川底の石さえも見えてしまうのでしょう。この白い石も艶々した白ではなく、ざらっとした冷たい感じがします。みどり深い山の中は、確かに太陽の光も届かず、湿っぽい感じがしますね。雨ではないのに、着ていたものがしっとり濡れる。ふるさと静岡の天城の山の中を歩いた時に、こんな感じだったような気がします。